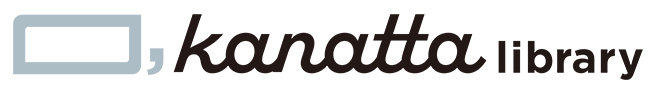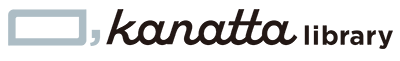「アップサイクル」で新たな価値を創造!今こそ「もったいない精神」を発揮させよう


みなさん、こんにちは!
コロナの影響で残念ながら延期になってしまった東京オリンピックは「レガシーを遺す」ことを大きな大会テーマとして掲げています。
その中でも、食品ロス削減を大きな目標の一つとして掲げていることをみなさんはご存知ですか?
というのも、日本は世界の中でも「フードロス大国」と呼ばれ、2019年において一人当たりの年間食品廃棄物量は世界で第6位、アジアではワースト1位となっています。
わたしは飲食系のアルバイトをしているのですが、毎日余った食品は廃棄処分しなければならず、満帆のごみ袋を数袋営業後に捨て、「食べられるのにな…もったいないな…」なんて毎日心を痛めています。
今回は、そんな日本で行なわれているフードロス削減に向けた取り組みを紹介します。
「もったいない精神」の歴史

今では「フードロス大国」なんて呼ばれている日本ですが、少し前までは超循環型社会だったということをご存知ですか?
「もったいない」
みなさんにとってはなじみのある言葉ですよね。
この「もったいない」という考え方は日本特有のものなのです。
今では、「MOTTAINAI」という日本語が国際言語となり、環境問題に関する議論の中で非常に注目を集めるようになりました。
「もったいない」は、日本の仏教思想に由来しています。
(東洋経済オンラインより参照)
この精神は、江戸時代に強く生きており、完全な循環型社会を実現していました。
徳川家康時代に人工的に建造された江戸町では、当初ごみの廃棄問題に悩ませられていました。
しかし、その後日本の「もったいない精神」が開花し、衣食住に関わるものはすべてリユース・リデュース・リサイクル・リペアされ、美しい環境が保たれていました。
そのような社会を再び取り戻したいですね。
「アップサイクル」とは?

そんなフードロス問題で今注目されているのが「アップサイクル食品」です。
アメリカで設立された「アップサイクル食品協会」(本部コロラド州デンバー)が制定したアップサイクルの定義は、
「本来は人間の食用にされなかった原材料を用い、検証可能なサプライチェーンで調達・生産され、環境に良い影響をもたらす食品」
(ForbesJAPANより引用)
少し分かりにくいと思うので、言い換えてみると、廃棄予定のモノを原料に戻して新たな形に生まれ変わらせるリサイクルや、不用品をそのままの形で違う用途で使用したり、誰かに譲って使ってもらったりするリユースとも違い、今まで価値を見出されてこなかった廃棄物に新たな価値を生み出し、廃棄物を減らすという取り組みが「アップサイクル」と呼ばれます。
日本で行なわれている具体的な事例

実際に「アップサイクル」が日本でどのように行なわれているかを紹介します。
1.Farm Canning
”無農薬栽培、有機栽培といった持続可能な農業に従事する生産者から、色や形が不揃いといった理由でB級品(規格外)となる”もったいない野菜”を直接仕入れます。
廃棄されてしまう運命だった野菜たちを使った瓶詰めの製造販売、ケータリングなどによる食の提供を通じ、持続可能な一次産業をサポートします。”
FARM CANNINGより引用
2.こんにゃくセラミド健美肌プロジェクト
”「こんにゃくセラミド」は、一般的なこんにゃくを作る過程で取り除かれてしまう「飛び粉」に含まれています。飛び粉から抽出したセラミドは資源の有効利用として環境にもやさしい素材であり、全身のバリア機能を強化し、身体の内部からセラミドの産生を促進する効果が期待できる私たちの美しく健康的な肌に欠かせない成分でもあります。”
(こんにゃくセラミド健美肌プロジェクトより引用)
3.Kai’s Kitchen
雑魚やマイナー魚、未利用魚と呼ばれて廃棄される魚たちに新たな価値を見出し、その日に取れた魚に合わせて料理を提供するお店です。
(Kai’s Kitchenより引用)
まとめ

いかがでしたか?
「アップサイクル」という考え方がもっと広がってくれば、いずれ「ゴミって何?」という世界が来るかもしれませんね。
日本特有の価値観「もったいない」精神に立ち返り、「アップサイクル」を通して、「フードロス大国ニッポン」から世界のフードロス問題を牽引するリーダー国を目指しましょう!
———
ライター:早稲田大学 平田唯
SDGs、エシカルについて、まずは知ることから始めたい方は、このkanatta libraryを、
最新情報を知りたい、また、ご自身で情報発信したり、情報交換していきたい方は、Facebookコミュニティへ、
この記事をきっかけに、少しでも「株式会社Kanatta」に興味を持たれた方、活動してみたい方は是非チェックしてみてください。